金融市場NOW
円高とG7協調円売り介入について
2011年04月01日号
- 金融市場の動向や金融市場の旬な話題の分析と解説を行います。
- 生損保のリパトリエーション(資産の国内回帰)を背景とした足元の円高は根拠に薄く投機的色彩が濃い。
- 為替介入警戒感は事あるごとにくすぶり続け、円高の牽制要因に。
東北地方太平洋沖地震を受け、保険金支払いに充てる円資金需要から「生損保が海外資産の売却(リパトリエーション)に走る」との投機的思惑から、ドル/円は一時76円台まで円高が進行しました。これに対し、主要7ヵ国は「為替レートの過度な変動や無秩序な動きは経済・金融の安定に悪影響を与える」と声明し、ドル/円では1995年以来の協調円売り介入を実施しました(3月18日)。協調介入を含む過去の円売り介入は時間差を伴いながらも、一定の効果を上げてきたようです(グラフ1)。日銀単独の円売り介入は、大企業の年度計画想定為替レート(日銀短観)に対して大幅な円高水準で実施される傾向があります(グラフ2)。今後も単独・協調介入に対する警戒感はくすぶり続け、急激な円高の牽制になるものと考えます。
グラフ1
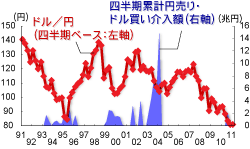
グラフ2
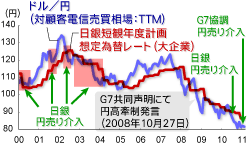
一時76円台まで進んだ円高の材料に挙げられていたのは 生損保のリパトリエーションへの思惑です。その実現可能性を占う上で、阪神淡路大震災当時のリパトリエーションの動向を見てみました。データを見る限り、当時の生保が、海外資産を売却した形跡はありません(グラフ3)。また当時の再保険収支が黒字化(円高圧力)してもいません(グラフ4)。仮に、生保が保険金を捻出する必要があるとしたら、それは海外資産の売却よりも、むしろ残高を積みましてきた国内資産の売却が妥当ではないかと考えます(グラフ5)。従って、リパトリエーション観測を背景とした足元の円高は根拠が薄く、投機的な色彩が濃いものと考えます。与謝野経済財政相は「生損保のリパトリエーションの噂は事実と異なる。保険金支払いは国内の円資金で十分。保険金支払い総額は5,000億円にも満たない」とコメントしています。
グラフ3
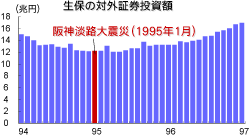
グラフ4
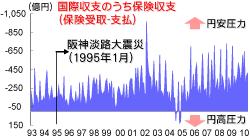
グラフ5
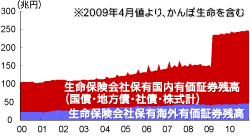
グラフ6
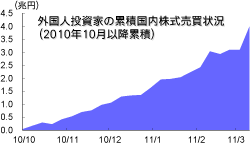
生損保の日本へのリパトリエーションばかりが注目され、投機の材料にされていますが、昨年10月以降、累積約3兆円の買越しとなっている外国人投資家の対日株式投資フローがリスク回避により、リパトリエーションした場合は円安への思惑が台頭することも視野に入れなくてはなりません(グラフ6)。
金融市場動向
関連記事
- 2025年02月20日号
- 機械学習の手法を活用しシクリカル株に投資(前編)
- 2025年01月23日号
- 成長性を評価する定量指標(1)
- 2025年01月17日号
- 【アナリストの眼】データが導くヘルスケアのイノベーション
- 2024年12月13日号
- 【アナリストの眼】食品企業の挑戦:インフレ継続をチャンスに変えられるか
- 2024年11月18日号
- 【アナリストの眼】KDDIがローソンと挑む「ソーシャル・インパクト」は、株主の期待に応えられるか?
「金融市場動向」ご利用にあたっての留意点
当資料は、市場環境に関する情報の提供を目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものであり、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 手数料や報酬等の種類ごとの金額及びその合計額については、具体的な商品を勧誘するものではないので、表示することができません。
- 投資する有価証券の価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。
