金融市場NOW
デフレと円高、追加緩和策と為替介入について
2010年09月01日号
- 金融市場の動向や金融市場の旬な話題の分析と解説を行います。
- デフレによる日本の実質金利上昇は円高要因の一つ。
- デフレ阻止を含む為替介入は円高牽制の選択肢の一つであり、80円割れ水準や円高スピード加速局面では警戒が必要。
デフレとは簡単に言うと、物価が持続的に下落してゆくことです。通貨の動向を決める重要な要素として実質金利(名目金利-消費者物価)が挙げられますが、デフレ環境下では、マイナスの消費者物価が実質金利の水準を高めます。このため先進国で唯一デフレ環境にある日本は、名目金利では世界最低水準にありますが、実質金利は高水準になってしまうのです(グラフ1)。約15年ぶりの円高要因の一つには、他国比で相対的に高い日本の実質金利も寄与している可能性があります(グラフ2)。
グラフ1
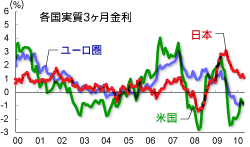
グラフ2
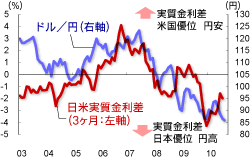
グラフ3
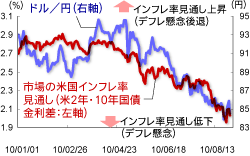
米国では一時、デフレ観測や追加金融緩和の思惑が急速に強まり、日米金利差の縮小から円高が進行しました。しかしその後、バーナンキFRB(連邦準備制度理事会)議長が「インフレ上昇のリスクも、大幅なデフレリスクも低いと思われる」と述べたことから、過剰なデフレ観測は落ち着きを取り戻した模様です(グラフ3)。
グラフ4
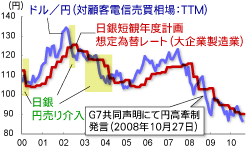
過去、政府・日銀は実勢レートが日銀短観想定レート(大企業製造業)を下回る水準で、市場介入、または口先介入を実施していました。今局面でも菅首相が為替の過度な変動に対し、必要に応じ「断固たる」措置を取ると表明しました。ただ、現状では為替介入による円安誘導は国際協調の観点から非現実的と考えられます(グラフ4)。
グラフ5
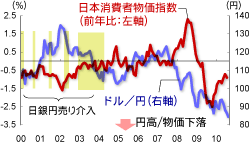
現在のデフレと円高の環境は、グラフ5四角囲い部分の介入局面とよく比較されます。特に、2003年の大規模介入はデフレ阻止が命題になっていました。このことを考慮すると、早期の介入は非現実的にしろ、今後、80円割れ水準や円高スピードが急加速する局面があれば、デフレ阻止を視野に入れた日銀による単独介入の可能性が高まることも想定されます(グラフ5)。
グラフ6
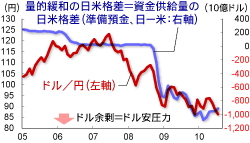
日米はそれぞれ金融緩和局面にあり、中央銀行が国債等を民間銀行から購入し、その代金を準備預金に払い込むことを通じ、資金の供給量を増やしています。これを量的緩和といいます。従って、日本との対比で過剰な米国の準備預金残高がドル安の一要因とされてきました。しかし、米国の経済安定化に伴う超緩和策からの脱却により、ドルの過剰供給ペースは鈍化しており、ドル余剰からのドル安圧力は概ね解消しつつあります(グラフ6)
金融市場動向
関連記事
- 2025年02月20日号
- 機械学習の手法を活用しシクリカル株に投資(前編)
- 2025年01月23日号
- 成長性を評価する定量指標(1)
- 2025年01月17日号
- 【アナリストの眼】データが導くヘルスケアのイノベーション
- 2024年12月13日号
- 【アナリストの眼】食品企業の挑戦:インフレ継続をチャンスに変えられるか
- 2024年11月18日号
- 【アナリストの眼】KDDIがローソンと挑む「ソーシャル・インパクト」は、株主の期待に応えられるか?
「金融市場動向」ご利用にあたっての留意点
当資料は、市場環境に関する情報の提供を目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものであり、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 手数料や報酬等の種類ごとの金額及びその合計額については、具体的な商品を勧誘するものではないので、表示することができません。
- 投資する有価証券の価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。
