金融市場NOW
人民元と中国経済の構造転換(輸出主導経済から内需主導経済へ)
2010年07月01日号
- 金融市場の動向や金融市場の旬な話題の分析と解説を行います。
- 中国の輸出依存度は高く、人民元の短期間での急激な上昇は、価格競争力の低下を通じ、輸出主導の中国経済にマイナス。
- 今後の人民元の柔軟性拡大を占うには、輸出主導経済から内需主導経済への構造転換の進捗動向がカギ。
中国人民銀行は、人民元の弾力性を高めると公表し、約2年間続けてきた事実上のドルペッグ制(固定相場制)の終了を示唆しました。市場では、この先1年で、人民元が約2%元高に振れることを織り込んでいる模様です(グラフ1)。購買力平価ベースの中国のドルベースGDP(2009年時点で8.8兆ドル)と実際のGDP(2009年時点で4.9兆ドル)の格差を見ると、人民元が約40%弱過小評価されていると見ることができます(グラフ2)。この先も、人民元の切り上げ圧力は継続しそうです。
グラフ1
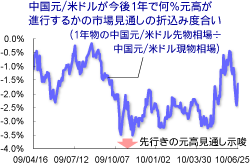
グラフ2
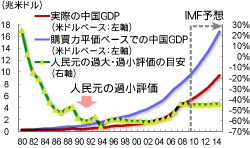
中国の通貨政策は、1973年に開始された円の変動相場制への歴史を踏襲しているように見えます(グラフ3)。ただ、当時の日本と現在の中国における貿易と内需の構造が大きく異なるため、人民元の変動相場制への道程は、日本のケースよりも多分に緩やかなものとなりそうです。
中国当局は輸出主導経済から内需主導経済(輸入増)への構造転換を標榜していますが、中国の輸出依存度は他国との比較(グラフ4)および、変動相場制に移行した当時の日本との比較(グラフ4)でも、傑出して大きくなっています。このため、急速な人民元の上昇は輸出主導経済に打撃となるため、現時点において、中国当局は容認できる段階にはないと思われます。
グラフ3
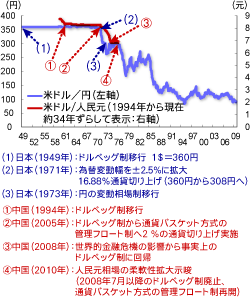
グラフ4
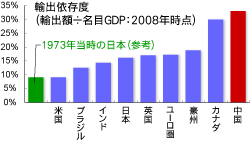
中国の民間最終消費支出の対GDP比は他国との比較および、変動相場制に移行した当時(1973年)の日本との比較でも低い水準にあります(グラフ5)。輸出主導経済から内需主導経済への転換を占う上で、労働者の賃上げを要求したストライキなどで報道されているように、賃金引き上げの潮流が拡大するかどうかに注目したいと思います。
中国の総固定資本形成(主に政府が行なう公共投資、公共事業)の対GDPが他国比で傑出しています(グラフ6)。外需と公的投資依存からの脱却、および内需主導経済への構造改革が本格的な人民元改革への条件と考えます。
グラフ5
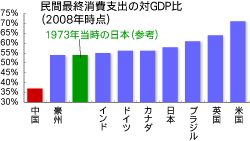
グラフ6
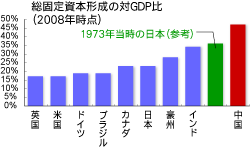
金融市場動向
関連記事
- 2025年02月20日号
- 機械学習の手法を活用しシクリカル株に投資(前編)
- 2025年01月23日号
- 成長性を評価する定量指標(1)
- 2025年01月17日号
- 【アナリストの眼】データが導くヘルスケアのイノベーション
- 2024年12月13日号
- 【アナリストの眼】食品企業の挑戦:インフレ継続をチャンスに変えられるか
- 2024年11月18日号
- 【アナリストの眼】KDDIがローソンと挑む「ソーシャル・インパクト」は、株主の期待に応えられるか?
「金融市場動向」ご利用にあたっての留意点
当資料は、市場環境に関する情報の提供を目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものであり、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 手数料や報酬等の種類ごとの金額及びその合計額については、具体的な商品を勧誘するものではないので、表示することができません。
- 投資する有価証券の価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。
