金融市場NOW
日本の財政悪化問題と金融市場(長期的視点)
2009年12月01日号
- 金融市場の動向や金融市場の旬な話題の分析と解説を行います。
- 日本の財政悪化問題は短期的には金利上昇や円安には直結しないが、長期的な金利上昇、円安リスクとして注意が必要。
グラフ1
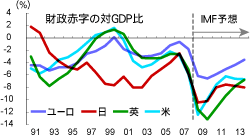
海外投資家を中心に日本の財政悪化問題に注目が集まっているようです。来年度の概算要求額が過去最大の95兆円に膨張する一方、税収が40兆円程度となる見通しの中では、新規国債発行額(44兆円)を上積みしても、84兆円にしかならず、結果、国債の増発懸念、財政悪化懸念が浮上したわけです。日本の財政赤字の対GDP比は悪化傾向を続けており、IMFの2014年までの予想では先進国中、最悪となる模様です(グラフ1参照)。また、政府債務残高の対GDP比は主要国の中で群を抜いて拡大しています(グラフ2参照)。一般に、財政悪化懸念は長期金利の上昇や通貨下落要因として解釈されますが、日本では過去そうなっていません(グラフ3参照)。これは、基本的に国内の貯蓄が豊富なため、海外資金に依存しなくても国債の消化(購入)が十分可能であったからだと考えられます。ただ長期的には、高齢化社会が進展し、国内の貯蓄取り崩しを見込んで国内資金の国債消化能力が無限でないとの認識が広がる可能性も指摘されており、財政規律の悪化が、悪い金利上昇(企業収益や経済の改善以上に財政懸念が金利を上昇させ、株価や地価が圧迫を受ける)、円安要因として、くすぶり続けるとの見方をする向きもあるようです。
グラフ2
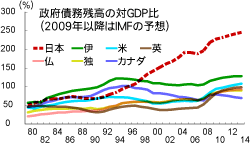
グラフ3
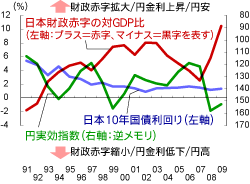
過去、日本の財政悪化問題は金利上昇や通貨安の要因にはなりませんでした。これは、基本的に国内の貯蓄が豊富なため、海外資金に依存しなくても国債の消化(購入)が十分可能であったからだと言われています。日本の国債は全体の60%弱が国内の金融機関によって保有されている一方、海外勢は5%程度の保有に留まっています(グラフ4参照)。また、家計の金融資産内訳の約60%は現金・預金であり、日本の家計は金融機関の預金を通して、間接的に国債の消化(購入)に貢献しているとも言えます(グラフ5参照)。このように、国債の買い手の資金(国内貯蓄)が豊富な場合は、財政規律の悪化が即、悪い金利上昇や円安には直結しにくいと考えられますが、2005年に人口が頭打ちし、かつ高齢化社会が進展中の日本において、労働人口が減少している事実は注視する必要があります。なぜなら、豊富な家計貯蓄が更に低下してゆくことが見込まれ、国債の消化を支えている資金源の減少が今後更に見込まれるからです(グラフ6)。また、銀行資産の配分上、自己資本規制や会計ルールの変更を考慮すると、債券保有比率が劇的に増加してゆくことも想定しにくい(グラフ7参照)こともあり、日本の財政問題は「国債の買い手不在」懸念が浮上する局面においては、長期的な金利上昇リスク、円安リスクとして具現化することになるのかもしれません。
グラフ4: 日本の国債の保有構造
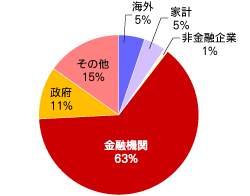
2009年6月時点
グラフ5:日本の家計の金融資産内訳
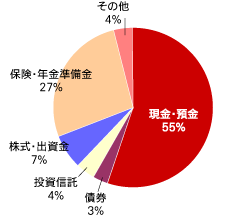
2009年6月時点
グラフ6
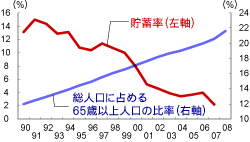
グラフ7
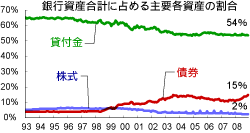
金融市場動向
関連記事
- 2025年02月20日号
- 機械学習の手法を活用しシクリカル株に投資(前編)
- 2025年01月23日号
- 成長性を評価する定量指標(1)
- 2025年01月17日号
- 【アナリストの眼】データが導くヘルスケアのイノベーション
- 2024年12月13日号
- 【アナリストの眼】食品企業の挑戦:インフレ継続をチャンスに変えられるか
- 2024年11月18日号
- 【アナリストの眼】KDDIがローソンと挑む「ソーシャル・インパクト」は、株主の期待に応えられるか?
「金融市場動向」ご利用にあたっての留意点
当資料は、市場環境に関する情報の提供を目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものであり、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 手数料や報酬等の種類ごとの金額及びその合計額については、具体的な商品を勧誘するものではないので、表示することができません。
- 投資する有価証券の価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。
