金融市場NOW
円キャリー取引(円借り取引)と円相場の関係
2009年09月01日号
- 金融市場の動向や金融市場の旬な話題の分析と解説を行います。
- 低金利の円で調達した資金を高金利国で運用し、金利差を利益の源泉とする取引を円キャリートレードという。
- 足元、市場の振れ幅(ボラティリティ)の低下から、金利差に着目した円キャリートレードが復活する兆しが出ている。
円キャリートレードを対主要通貨で行った場合の平均年間収益を見ると、マイナスとなったのが過去19年間で、7回、後の12回はプラスとなっています。マイナスの年が多いのは、90年代初頭です。この期間は米国の政治的円高圧力の時期等と符合しており、金利差は材料になりませんでした。他のマイナス計上年は、全て金融危機局面です。言い換えると、政治的円高圧力もしくは金融危機などの「異常な局面」以外の平常年で相対的に海外金利>日本金利の局面では、円キャリートレードは有益な投資手段であったようです。今年の年初来の同収益もプラスとなっており、円キャリー取引回復の兆候と見る向きがあるようです(グラフ1参照)。 年初来、8月19日までの円キャリー取引の各通貨別収益を見ると、金利差が高い国の通貨および、将来の利上げが視野に入り始めた国の通貨が上位にある傾向がみられるようになりました(グラフ2参照)。
グラフ1
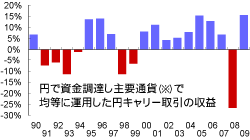
主要通貨=南アフリカランド、ブラジルレアル、豪ドル、ニュージーランドドル、ノルウェークローネ、スウェーデンクローナ、ポンド、カナダドル、韓国ウォン、デンマーククローネ、メキシコペソ、ユーロ、スイスフラン、シンガポールドル、台湾ドル、米ドル等
グラフ2
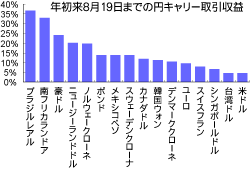
金利差が為替の動向と密接に連動する条件の一つは、為替の振れ幅(ボラティリティ)が低いということです。グラフ3、4の赤折線グラフは日本と豪米の3ヶ月金利差をインプライドボラティリティ(※)で割った円キャリー取引指数です。この指数の値が大きい局面では、金利差と為替の関係が強まる傾向が見られます。円キャリー取引収益の上位に位置している豪ドルの円キャリー取引指数は上昇傾向にあり、これに連れて豪ドル/円も連れ高しています(グラフ3参照)。言い換えるならば、豪州は円キャリー取引復活の条件が整い始めたと言うのでしょうか。一方、最下位に位置する米ドルは円キャリー取引指数が依然として低下しており、円キャリー取引復活の兆候は出ていない模様です(グラフ4参照)。
グラフ3
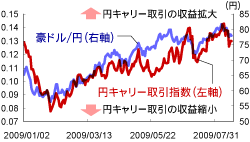
- 市場参加者が今後の相場変動をどのように考えているかを測る指標のひとつ。
グラフ4
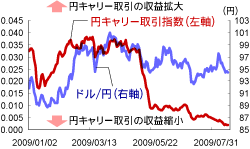
-
出所:ブルームバーグ
- 市場参加者が今後の相場変動をどのように考えているかを測る指標のひとつ。
円キャリー取引は日本と海外の金利差に着目した取引です。足元、再度、金利差に注目が集まるようになってきたようです。そうなれば、市場の注目は、利上げの可能性がある国を探すことです。超金融緩和から利上げに転ずる出口政策なる言葉がマスコミに出てきたのがその証左です。豪州や英国では弱いながらも来年の利上げ観測がくすぶり続けています。今後1年間に織り込まれている政策金利変化幅の豪州と英国の対日格差は、それぞれ豪州優位、英国優位になってきました。これに伴い、豪ドル、ポンドが上昇傾向にあります(グラフ5、6参照)。
グラフ5
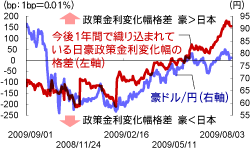
グラフ6
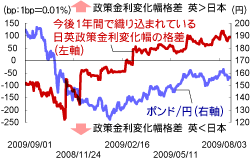
金融市場動向
関連記事
- 2025年02月20日号
- 機械学習の手法を活用しシクリカル株に投資(前編)
- 2025年01月23日号
- 成長性を評価する定量指標(1)
- 2025年01月17日号
- 【アナリストの眼】データが導くヘルスケアのイノベーション
- 2024年12月13日号
- 【アナリストの眼】食品企業の挑戦:インフレ継続をチャンスに変えられるか
- 2024年11月18日号
- 【アナリストの眼】KDDIがローソンと挑む「ソーシャル・インパクト」は、株主の期待に応えられるか?
「金融市場動向」ご利用にあたっての留意点
当資料は、市場環境に関する情報の提供を目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものであり、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 手数料や報酬等の種類ごとの金額及びその合計額については、具体的な商品を勧誘するものではないので、表示することができません。
- 投資する有価証券の価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。
