金融市場NOW
日米英の量的緩和について~今更聞けない量的緩和とは?~
2009年04月01日号
- 金融市場の動向や金融市場の旬な話題の分析と解説を行います。
日米に続き、3月5日には英国が量的緩和への移行を決定しました。今回は、そもそも量的緩和とは何なのかを紹介した上で、量的緩和が経済に与える影響に焦点を当ててみました。
量的緩和とは、中央銀行がマネタリーベース(現金+法定準備預金)の増加を意図したオペレーションを行うことを言います。通常、商業銀行は、お金の一定比率を中央銀行の法定準備預金に預けるよう義務付けられています。量的緩和とはこの法定準備預金の合計額を大幅に上回る目標金額を設定し、その目標金額に向けて、中央銀行が国債や社債等の証券を商業銀行から購入し、代金を法定準備預金に払い込むことを通して、お金の総量を増やすことです。増加した法定準備預金残高を商業銀行は貸出し等に充てることが可能になり、信用収縮の改善要因になります。量的緩和への移行が決定されると、法定準備預金残高が増加し(グラフ1、2)、同時にマネタリーベースも連動し増加することがわかります(グラフ1)。
(グラフ1)法定準備金とマネタリーベース (月次)
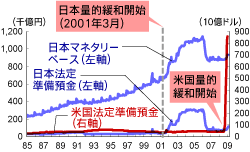
(グラフ2)英国の法定準備預金(週次)
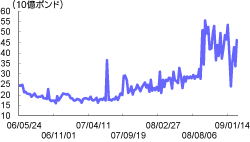
(グラフ3)日本のマネタリーベースと銀行貸出
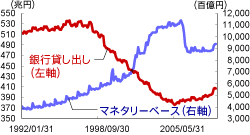
量的緩和が実体経済において効果を上げるには、金融機関が、法定準備預金への支払いを通じて供給された余剰なお金を家計や企業への貸出しに回すことが必須条件です。2001年以降の日本の量的緩和を見ると、お金の総量(マネタリーベース)は急激に上昇したにも関わらず、銀行貸出しは減少しました。つまり、結果だけを見ると、当時、銀行は、お金を貸出しに回さなかったようです。
(グラフ4)米国商業銀行 資産の推移(銀行信用と現金)
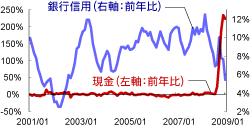
米国でも量的緩和は実施されており、中央銀行はコマーシャルペーパー(CP)、モーゲージ担保証券、エージェンシー債などを購入し、お金を供給し続けています。この結果、グラフ1にも見られるように法定準備預金の残高は急増しています。しかし、米国商業銀行の資産内容を見ると現金が急増する傍ら、銀行信用(貸出し)が急低下しています。前述グラフ3の日本の例と同じく、銀行は急増した法定準備預金を貸出しへ回すことには消極的な模様です。
(グラフ5)英国住宅ローン承認件数と金融機関の貸出状況
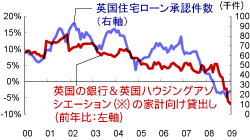
(※)日本で言う住宅金融公庫のようなもの
英国では、社債や国債が中央銀行の購入対象になり、量的緩和が実施されることが3月上旬に発表になりました。量的緩和に踏み切った背景の一つとして、金融機関の貸し渋りが挙げられていました。英国の金融機関の貸出し、および住宅ローン承認件数(注)の急減がこの証左です。今後は、量的緩和の進行により、貸出しが改善してくるのか要注目です。
- 住宅を購入したい人のローン申請に対して金融機関が何件の承認をしたのかを表すデータ
(グラフ6)日本の実質GDPと日本マネタリーベース
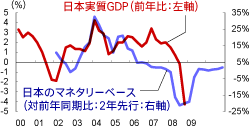
前述したように、量的緩和それ自体が経済の回復に効果を発揮するわけではありません。ただ、過去の日本の例を見る限り、量的緩和は約2年の時間差を伴い日本の景気回復に重要な役割を担っていたようです。日本の量的緩和は、バブル崩壊から約10年経過後に実施され、 「日本の失われた10年」をつくりました。一方、今局面の米英は同、約1年後に量的緩和を開始しています。対処の早さが危機の抑制につながることを期待したいものです。
金融市場動向
関連記事
- 2025年02月20日号
- 機械学習の手法を活用しシクリカル株に投資(前編)
- 2025年01月23日号
- 成長性を評価する定量指標(1)
- 2025年01月17日号
- 【アナリストの眼】データが導くヘルスケアのイノベーション
- 2024年12月13日号
- 【アナリストの眼】食品企業の挑戦:インフレ継続をチャンスに変えられるか
- 2024年11月18日号
- 【アナリストの眼】KDDIがローソンと挑む「ソーシャル・インパクト」は、株主の期待に応えられるか?
「金融市場動向」ご利用にあたっての留意点
当資料は、市場環境に関する情報の提供を目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものであり、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 手数料や報酬等の種類ごとの金額及びその合計額については、具体的な商品を勧誘するものではないので、表示することができません。
- 投資する有価証券の価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。
