金融市場NOW
米国投資資金のリパトリエーション(投資資金の自国回帰)によるドル高の議論
2008年10月01日号
- 金融市場の動向や金融市場の旬な話題の分析と解説を行います。
米国での金融危機を受けた米国投資家のリスク回避が強まり、世界中に投資された米国ヘッジファンドを中心とした投資家の資金が米国に回帰する(リパトリエーション)ためにドルの買い戻しが起きるとの議論があります。今回は、この議論について考えてみたいと思います。
(グラフ1)米国 証券投資 流入/流出状況
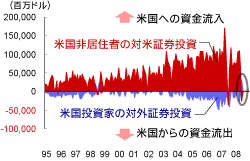
リパトリエーションによるドル高が起きるとすれば、少なくとも、米国への資金回帰(ドル買い圧力)>米国からの資金流出(ドル売り圧力)の関係が成立しなければなりません。しかし、世界規模のリパトリエーションが起きたと仮定した上で、右グラフ(1)を見ると、米国投資家の対外証券投資額(潜在的なドル買い圧力)<米国非居住者の対米証券投資額(潜在的なドル売り圧力)となっています。足元は、確かに米国投資家の国内回帰(海外証券の売り越し)が起きていますが、その一方、米国非居住者の米国証券の売り越しがほぼ同金額出ています。従って、為替への影響は双方向の売り越しとなり、相殺となっています(グラフ(1)丸囲い部分)。
米国投資家は、過去の金融危機局面(1998年:LTCM破綻、2001年:ITバブル崩壊、同時多発テロ)では、外国債券および外国株式を売り越し、自国に投資資金を一旦引き上げた(リパトリエーション)と言われています。しかし、ドルとリパトリエーションの動向(海外債券・海外株式の売りこし)には密接な連動は見られないようです。また、米国の投資家の海外債券および海外株式の売り越し期間は短期間であり、長期に渡り為替市場に影響を与え続ける要因にはなりにくいようです。
(グラフ2)米国投資家の対外債券投資とドル
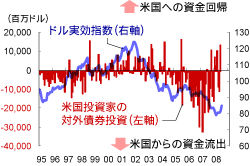
(グラフ3)米国投資家の対外株式投資とドル
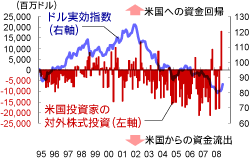
欧州や豪州など米国以外の景況感が急速に後退したことや、米国投資家のリパトリエーションの思惑を受けて7月中旬以降、ドルの全面高が進行していました。この影響等もあり、円は対ユーロや対豪ドルを中心に円高の展開となっていました。しかし、米国金融不安の再燃等からドルが反落するに連れ、ユーロ/円、豪ドル/円も直近の安値からそれぞれ約7円~約8円ほど円安方向に反発しています。前述の通り、米国投資家のリパトリエーションを背景としたドル高観測が長期化する可能性が低いことを考慮すると、金融不安当事国として不安を抱える米ドルの全面高は目先、維持しにくくなります。その場合は、対円でのユーロ安、豪ドル安圧力も後退しそうです。実際、今後1年間に織り込まれている日本とユーロ圏および豪州の政策金利変化幅の格差は更なる円高が進行する可能性が限られていることを示唆しているように見えます。
(グラフ4)今後1年間で織り込まれている日米政策金利変化幅格差(※)とドル/円
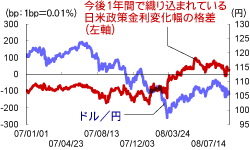
- OIS市場ベースで算出
(グラフ5)今後1年間で織り込まれている日欧政策金利変化幅格差(※)とユーロ/円
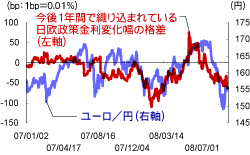
- OIS市場ベースで算出
(グラフ6)今後1年間で織り込まれている日豪政策金利変化幅格差(※)と豪ドル/円
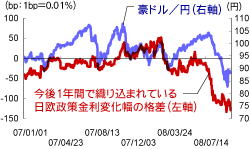
- OIS市場ベースで算出
金融市場動向
関連記事
- 2025年02月20日号
- 機械学習の手法を活用しシクリカル株に投資(前編)
- 2025年01月23日号
- 成長性を評価する定量指標(1)
- 2025年01月17日号
- 【アナリストの眼】データが導くヘルスケアのイノベーション
- 2024年12月13日号
- 【アナリストの眼】食品企業の挑戦:インフレ継続をチャンスに変えられるか
- 2024年11月18日号
- 【アナリストの眼】KDDIがローソンと挑む「ソーシャル・インパクト」は、株主の期待に応えられるか?
「金融市場動向」ご利用にあたっての留意点
当資料は、市場環境に関する情報の提供を目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものであり、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 手数料や報酬等の種類ごとの金額及びその合計額については、具体的な商品を勧誘するものではないので、表示することができません。
- 投資する有価証券の価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。
