金融市場NOW
カネ余り状態と資産価値高騰の関係
2008年08月01日号
- 金融市場の動向や金融市場の旬な話題の分析と解説を行います。
バブルを含む資産価値高騰の背景には、往々にして過剰な金融緩和によって引き起こされたカネ余り状態が介在しています。足元では、原油価格を中心としたコモディティ価格の高騰がバブルだと見る向きもあります。今回は、原油バブル?の背景にあると思われる金余りシステムの一つに目を向けてみました。
前述の通り、資産価値高騰の背景には、往々にして、大幅な金融緩和によって引き起こされたカネ余り状態が介在しています。例えば、過去の米国株の本格上昇の契機の一つとなったのは、実質マイナス政策金利にまで緩和された米国の大幅な金融緩和がありました(グラフ1参照)。年初以降の相場で高騰している資産を見ると、原油を中心としたコモディティ価格が唯一であり、他の資産は低迷しています(グラフ2参照)。このため、世界の投資資金は高い収益を求め、急激に原油市場に流入したわけです。原油価格高騰の背景にもカネ余りシステムが介在しているのでしょうか?
(グラフ1)米国の実質政策金利と米国株
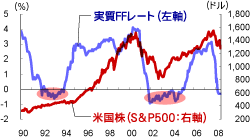
(グラフ2)各資産の推移 2008年1月1日=100として指数化
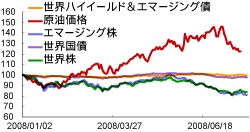
(グラフ3)中東産油国の消費者物価と通貨供給量(M2(※))
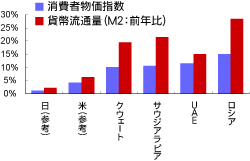
- M2:通貨供給量の代表的指標
中東産油国の多くは、自国通貨の変動を米ドルに連動させるドルペッグ制を主に採用しています。このため、時に、自国の経済実体にそぐわないにも関わらず、米国の金融政策に追随することになります。米国では景気の減速から、昨年夏場より、断続的な金融緩和が実施されてきましたが、中東諸国は、この間、好景気+2ケタ台のインフレ高進にも関わらず、米国に従い過剰なオカネを供給してきました。これが中東におけるカネ余りの根源で、オイルマネーの一端です。オイルマネーが高い収益を求めて原油市場に流入し価格を吊り上げているとの観測は後を絶ちません。
(グラフ4)中東諸国の経常収支と原油価格
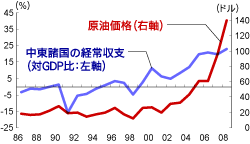
原油価格の高騰を受けて、世界有数の原油輸出国の集まる中東では経常収支黒字が累積しています。原油高効果が輸出額の増加につながり、経済全体を加速させ、インフレを高進させているのですが、多くの国がドルペッグ制を採用しているため、本来、採るべき金融引き締め策が実施できず、米国に合わせた緩和的な金融政策を実施しています。このため経済実体とかけ離れた過剰なオカネが供給され続けています。
(グラフ5)中東諸国の貯蓄と投資バランス
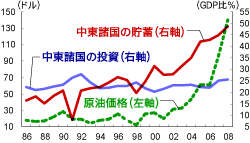
原油価格の高騰で得た利益は、中東諸国の経済を活発化させます。これによって生じる急激なマネーの増加率は投資の増加率を上回るスピードで増えているため、中東諸国では貯蓄過多な状態となっています。これもカネ余りの証左であり、潜在的な投資資金が潤沢である状態と言えます。この環境が原油の急落等を契機として解消に向かうまで、いわゆるオイルマネーは、原油に限らず、有利な投資先を模索し続けるのでしょう。
金融市場動向
関連記事
- 2025年02月20日号
- 機械学習の手法を活用しシクリカル株に投資(前編)
- 2025年01月23日号
- 成長性を評価する定量指標(1)
- 2025年01月17日号
- 【アナリストの眼】データが導くヘルスケアのイノベーション
- 2024年12月13日号
- 【アナリストの眼】食品企業の挑戦:インフレ継続をチャンスに変えられるか
- 2024年11月18日号
- 【アナリストの眼】KDDIがローソンと挑む「ソーシャル・インパクト」は、株主の期待に応えられるか?
「金融市場動向」ご利用にあたっての留意点
当資料は、市場環境に関する情報の提供を目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものであり、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。
【当資料に関する留意点】
- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 手数料や報酬等の種類ごとの金額及びその合計額については、具体的な商品を勧誘するものではないので、表示することができません。
- 投資する有価証券の価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。
